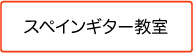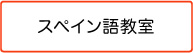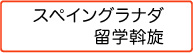①良いギターとは
良いギターとは、簡潔に、良く鳴るギターと要約出来るでしょう。鳴らないギターでは自分の思った様に音が出てくれず、やる気を削がれ、ましてや、音楽表現どころではありません。逆に、良く鳴るギターは自ずと弾き手をその気にさせてくれ、上達を促します。
従って、最初から良い楽器を持った方が上達すると言うのは、楽器商のセールス文句である反面、真理を突いています。やはり、ある程度以上の楽器は上達の必要条件です。ギター奏者は他のギター奏者にも、そして、良いギターにも刺激を受けて上達して行く事実は私自身の実感でもあります。
そして、誰でも同じ代金を払うなら、より良いギターを求めたいと思うのは当然です。一般的には、より高価である程、より良いギターだと言って宜しいでしょう。そのギター料金の相違と是非は別項で述べますが、ここでは普及モデル(量産ギター)から高級手工品に至る、総てのギターの規範たるべき、この掴み所のない良いギター、特に良いスペインギターの観点から、セファルディ流定義を試みてみます。読者の皆さん、掴んで下さい。
音量について
良く鳴るギターなら音が大きいはずだと言う単純な答えが返って来そうですが、問題は、その大きな音がどの様に弾けば出るギターかと言うことなのです。例えば、軽自動車で精一杯アクセルを踏み込んでも、ベンツで軽く流しても、時速100kmは時速100kmですが・・・。
良いギターの第一条件は、軽いタッチで音が気持ち良く出るギターと言えるでしょう。逆に、音が今一抜けないギターは、やはり今一です。バッティングは手応え、りんごは歯応え、ギターも弾き応えです。打てば響く太鼓の如く、まずは、ギターを軽く爪弾いただけでスキッと音が抜けるか、少々力を込めなければ音が出ないかが判断基準です。
同時に、少々力を込めなければ音が出ないギターには、次で述べる音質がなく、軽いタッチで音が自ずと出てくれるギターは、次項の[音質について]の[A]~[D]もまた、それなりに伴ってくれます。
それ故、最も端的なギター選考基準は、パリッとした歯応えの煎餅なら可、湿気っていれば不可だと比喩すれば分かり易いでしょう。但し、最初は鳴らず、弾き込むと明らかに音量音質を増すギターもありますので、ギターの良し悪しは、第一印象だけでは、一概に判断出来ない面も大いにあります。
セファルディからお届けするスペイン製普及モデル(料金一覧表の198,000円以下のギター&セラック手塗りGLシリーズ28万円)はセファルディがプルデンシオ・サエス製作所に指定する音量増幅内部構造です。店長の発案ではありませんが、何人もの有名な製作家が一昔前から実践している構造です(もちろん、この様式を用いない名工も多くいます)。ギターは生物ですから一概に言えませんが、この構造にすれば、平均して音量が増すことは統計上明らかです。
さて、初心者に限らず、上級者まで、この音量だけでギターを判断している、つまり、音が大きい方が良いギターであり、高価なギターほど音が大きいはずだと判断している人が結構いると思われます。しかし、量より質は人生の総ての面において、そして、音量より音質はギターのみならず、総ての楽器に共通して言えることです。従って、次の[音質について]の項目こそ、最も重要なギター選択基準です。少々長いですが、私も力を込めた項目ですので、克目してお読み下さい。
音質について
音量だけでなく、更に、それが味のある音である時、音質のあるギターだと言えます。たとえ量は同じでも、歯答えのある麺とない麺、スペインではこくのあるオーリブ油とないオリーブ油とも比喩出来ます。こくも味のある音も、中々言葉にならず、敢えて言えば、単に音が出ている以上の音なのでしょうが、これではますます分かりません。結局、何本も弾き比べて、耳を肥す以外にないのですが、それは、色々食べ歩く内に、いつの間にか舌が肥えて来ることにも似ています。
私が幼い頃からインスタントラーメンはありました。今では、これがインスタントかと思う様な美味しい製品もありますが、翌日、手打ちラーメンを食べれば違いは歴然です。確かに、見た目は両者共、丼一杯の同じ量のラーメンで、歴然とした違いはありませんが、そこに至る労力、過程、風味、歯応え、味、料金の違いは歴然です。わざわざラーメン屋まで出向いて手打ちラーメンを食べる人は、量ではなく、この歴然とした質の違いにインスタントラーメンより高いお金を払うと言えます。この歴然とした違いが良く分かっている人は、手打ちラーメンの方が歴然と高くても文句は言いません。見た目の量ではなく、味覚に訴える味が歴然と違うからです。
同様に、ギター奏者にとっても、ギターの音量の大小ではなく、音の味覚に訴える、味とこくのある音質こそ、ギター選択の一番の判断基準であるべきです。
************
とは言え、これではまだまだ抽象的表現の域を出ません。更に、幾つかの観点から、この音質のあるギターとは具体的に如何なるギターかについて、分かり易く見てみましょう。
【A】音の分離と遠達力
ギターは一度に6つの音まで同時に出る訳ですが、いくら音量があっても、各音が分離せず団子状態なら、今一つ釈然としない響き方をします。私は数十年前の安物のスペイン製くるみギターを持っています。当時は合板がなかった時代でしたので、安物とは言え、単板ギターですが、徹底的に経費節減したものと見え、何と内部には力木さえありません。ところが、おそらく経過年数のせいでしょう。このギターが手元で弾いた感じ、音は非常に小さいのですが、他の手工ギターを差し置き、何と聞く人総てにこのギターが一番良いと言われます。具体的には、一音一音がはっきり分離しており、遠くまできれいに聞こえると言うのです。また、私がグラナダ居住中の1990年、R.ブーシェのギターを弾く機会がありました。正直、手元での響きは、これが銘器かなあと言う第一印象だったのですが、プロがステージで弾くと、心に沁みる様な音色が客席の最後列まで余裕で響いて来ました。
音が分離しているが故に、軽いタッチで音に遠達力のあるギターこそ良いギターだと言えます。これを裏打ちする、以前読んだ、ある歌舞伎の師匠の逸話をご紹介します。マイクも何もない歌舞伎だからこそ、舞台の一番奥まで声を届かせるには声量だと思っていたその師匠は、ある日、ある女性ピアニストについて、”彼女の音は一音一音はっきり分離してきれいだ“との小澤征爾氏のコメントを聞き、母音をはっきり発音してやれば、声は張り上げなくとも、声は舞台の奥まで届くことを悟ったそうです。良いギターも同じです。各音が分離していれば、遠達力に優れ、手元の音量はそれ程ではなくとも、大きく聞こえるものです。また、その様なギターの音色には、必ず、味とこくと、そして、次に述べる個性が伴います。世の多くのギタリスト達の一番の判断基準もここにあります。
【B】個性ある音色
これもまた、掴み所のない表現ですが、スペイン人製作家やギタリストはギターを評価する際、”個性ある音色だから、これは良いギターだ”とか、”このギターは音に個性がない“とよく言います。
上の例で言えば、インスタントラーメンも手打ちラーメンも、何を食べても皆同じと言う人は味覚がない、つまり、手打ちラーメンの良さ、その個性が分からない味覚音痴だと言えます。ラーメンはともかく、コーヒーとなれば、正直、インスタントも専門店のコーヒーも、余り違いが分からない人も結構いるのではないでしょうか? コーヒーの個性を知覚する味覚がないと言えます。
同様に、ただ鳴っているだけではなく、音色が個性的だと違いの分かるスペイン人ギタリストは、”このギターは個性ある良いギターだ“との言い回しを用います。また、個性的な自分だけの音色のギターを作れる人が優れた製作家であり、それがその人の作風とも言えるでしょう。
【C】歌うギター
この歌うとは、私の師匠、故マヌエル・カーノ先生と息子ホセ・マヌエル・カーノが良いギターを形容する際、良く聞かされた表現です。それも、何分か試奏した後ではなく、弾き始めてすぐ口にする文句です。正に、名人は名器を知る、しかも、初見で知る。単音を爪弾くだけで、コードを押さえて、一度掻き鳴らすだけで、果たしてこのギターは歌うか否か、聴く耳を持っている人は利きます。
それは、あたかも、日本では利き酒、スペインではワインやオリーブ油を利く職人が、味とこくを舌で即座に利き分け、”良し!!“と頷く様なもの。ギターも楽器一般の選択も、言葉を変えれば、結局は利くこと、そして、利く耳を持っているか否かに換言出来ます。その時、酒やワインなら美味く、良いギターなら自ずと歌うギターであり、自ずと弾き手をも歌い奏でることに誘(いざな)います。
【D】包容力
良いギターを包容力と描写するのは、もしかすると世界中で私が初めてかも知れません。これはギターに限ったことではなく、上手い演奏は、楽器でも声楽でも、聴く人を包み込むふくよかさが感じられます。それは単に楽譜通り音が出ている以上の、奏者の豊かな表現力の表れです。
女性が男性に求めるものの一つがこの包容力かも知れませんが、男女を問わず、人間性に奥行きのある人は無言の内に包容力を感じさせます。それは良いギターも同じこと。包容力ある歌心のギター奏者は、類は友を呼んで、包容力のある音色のギターと出会うのかも知れません。
いわゆる箱鳴りではなく、ギター全体が鳴り、更に、奏者の後ろから音が泉の様に湧き出ていると感じるギターこそ、包容力のある良いギターだと言えるでしょう。
************
インスタントラーメンも手打ちラーメンも丼一杯のラーメンです。安物ワインも年代物ワインもグラス一杯のワインなのです。何が同じでしょうか? 量です。それでは、どちらが美味しいでしょうか? 後者です。同様に、ギターも音量ではなく、音色が美味しいかどうか、つまり、味とこくこそ、判断の一番の決め手であるべきです。味とこくのある音色のギターなら、以上【A.B.C.D】も 伴い、【A.B.C.D】が感じらるギターなら、それに応じた味とこくの伴うギターでもあるはずです。しかし、味とこくと言われても、掴み所がありません。結局、何軒も食べ歩かなければ、ラーメンも比較出来ない様に、ギターも何台も弾いて耳を肥やすしかありません。
バランスについて
弦によって、フレットによって、音量音質のバラつきがなく一定であること。
但し、どんな名器も、このフレットだけは音が弱いみたいな弱点は必ずあるものです。その意味では、ギターの選択は、どこで妥協するかと言う、妥協点の問題とも言えます。
敢えて、バランスの良し悪しの参考基準を挙げるなら、音質に優れたギターはまた、バランスも良く、バランスの良いギターはまた、音質にも優れているものです。
弾き易さについて
ある程度上達すれば、少々のサイズの問題は慣れの問題だとも言えますが、特に、初心者の内は、力みを伴うおかしな癖が付かないように、ネックの幅、太さ、弦長、弦高など、弾き手に無理のないサイズであることが必要です。
そのため、初心者は弾き易さと力む癖を付けないことを最優先して、少々の雑音は覚悟で、ブリッジの骨を削って弦を低めに張ったり、張力の弱いローテンション弦を使用しても差し支えないと思います。詳しくはこちらをご覧下さい。
セファルディでは、手の小さな人、女性子供用サイズのスペイン製ギターを用意しています。料金一覧表で弦長630&640&645㎜のギターをご覧下さい。
総括
その他、しっかりした作り、内部構造、仕上げの美しさ、塗装など、幾らでも述べることが出来ますが、一応、これらがセファルディ流良いギターの基本的な4項目(音量,音質,バランス,弾き易さ)です。
実際のところ、総てにおいて満足の行くギターと言うのは、如何に名工の作品でも中々ないものです。その意味では、ギターの選択はどこで妥協するかとも言えます。ただ、人によって、その妥協点が高いか低いかと言うことなのです。そして、味とこくを聞き分ける耳が養われて来る程に、良いギターの妥協点は高くなります。
以上、良いギターについて、木工ではなく、音の観点から述べたことに留意して下さい。
以前、どこかの高校野球の監督さんが”野球は勝った方が強い“と言ったことがありました。同様に、その調べによって、奏者も聴く人も豊かになるべきギターの最終目的から言えば、”ギターは鳴った方が良いギター”なのです。ただし、鳴り方は音質を一番の判断基準にして下さい。
読者の皆さん一人一人が良いスペインギターに出会うことを切に願います(代表)。
- «
- <
- 1
- >
- »